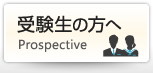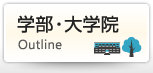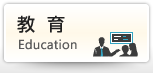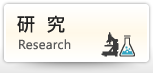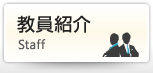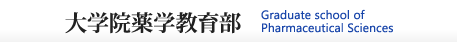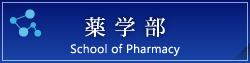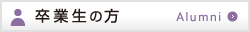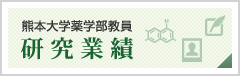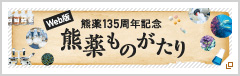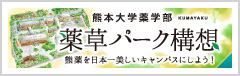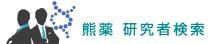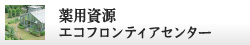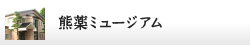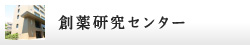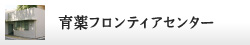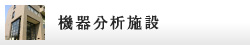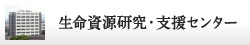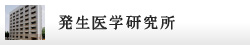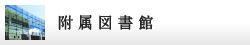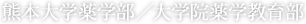薬学部長のあいさつ
『歴史と伝統に支えられ、アートとサイエンスの共存する熊本大学薬学部』
薬学部長 香月 博志

熊本大学薬学部は「熊薬(くまやく)」の通称で知られており、その源流は江戸時代中期、宝暦6年(1756年)に肥後熊本藩主の開設した「蕃滋園(ばんじえん)」という薬園にまで遡ることができます。近代教育機関としての熊薬は、明治18年(1885年)に設立された私立熊本薬学校が始まりで、同校はその後私立九州薬学校、私立九州薬学専門学校を経て大正14年(1925年)に官立の熊本薬学専門学校となりました。当時の旧制薬学専門学校の多くは調剤を専門とする薬剤師の養成機関でしたが、熊薬は昭和20年(1945年)に製薬学科を設置し、創薬研究者の養成も薬学の使命であることを全国に先駆けて示しました。その後、昭和24年(1949年)の熊本大学設置にあたって、熊本薬学専門学校は旧制第五高等学校などとともに新制大学に包括され、熊本大学薬学部としてのあゆみを始めました。熊薬は令和7年(2025年)には私立熊本薬学校設立から140周年、官立熊本薬学専門学校開校から100周年を迎えており、これまで多くの優秀な卒業生を輩出し、薬学の発展に大きく貢献してきました。

現在の熊薬は、6年制の薬学科と4年制の創薬・生命薬科学科の2学科を設置しています。薬学科では主に医薬品を適正に使用し、また使いやすいものに育てる「育薬」に携わる人材を、創薬・生命薬科学科では主に未来の新しい薬を作り出す「創薬」に携わる人材を育成しています。
高齢化社会の進展や医療技術の進歩など、社会や医療を取り巻く状況が刻々と変化を続けていく中で、医薬を通じて社会・医療に貢献する人材は、生涯にわたって研鑽を続け、専門家としての資質・能力を高めていくことが求められます。熊薬では、1年次のカリキュラムから薬学の専門教育科目を積極的に取り入れ、また早期体験学習などを通じて卒業後の進路にさまざまな選択肢があることを認識できるようにしています。薬学を構成する科目群のなかでも基盤的科目については概ね2年次後学期までに履修し、3年次以降はより応用的な科目群を履修するとともに、配属された研究室で特別実習(卒業研究)に取り組みことになります。特別実習は、答えの見つかっていない新たな課題を設定し解決していく過程を積み重ねていくもので、「生涯研鑽のミニチュア版」とも言える実習であり、熊薬のカリキュラムにおいても特に重要なものとして位置づけられています。
学部学生の皆さんが特別実習を実施する熊薬(関連施設を含む)の研究室は、物理系、化学系、生物系、臨床系をはじめとして薬学を支える多様な研究領域(28研究室:令和7年度時点)で構成されており、それらの研究室が互いに連携しながら研究を進めています。具体的な研究内容は各研究室のWebサイトで紹介されている通りですが、未来の医療を開拓していく原動力となる最先端の研究が展開されています。また、大学院生命科学研究部附属のグローバル天然物科学研究センターならびにワクチン開発研究センターは、複数の薬学部教員が運営を担っている研究センターであり、前者は世界中の薬用天然資源を基にした新薬の創出、後者は画期的ワクチンの開発に向けた先端的研究に取り組んでいます。学生の皆さんも、これらの研究に自ら携わることで薬学の専門家としての能力が磨かれていくことになります。
熊薬は旧制専門学校時代からの広大なキャンパスを受け継ぎ、敷地内にグラウンドや体育館も保有しています。キャンパス内の薬用植物園は、希少植物を含む2,000種あまりの薬用植物を守り育てつつ、一般の皆様にも自由に見学していただけるよう開放しています。熊薬ミュージアムでは、古い医学書や珍しい実験器具などの貴重な史料、世界の薬草など、熊薬とくすりに関するさまざまな資料を展示しています。さらに、キャンパス内のさまざまな場所に彫刻や絵画が配置されており、建物の一画にはフェルメール全37作の「リ・クリエイト」を一堂に展示した空間もあります。このように、熊薬はアート、薬草、そしてサイエンスが共存する全国に類を見ないクリエイティブな教育研究環境を提供しています。学生の皆さんには、是非この恵まれた環境を活用して薬学の専門家としての能力を磨き、将来社会へ羽ばたいていく上で必要な自らのポテンシャルを存分に高めていってもらいたいと思います。