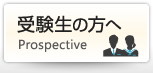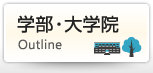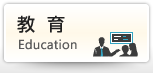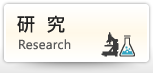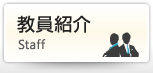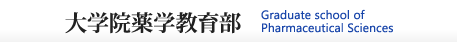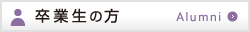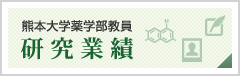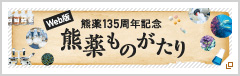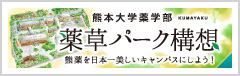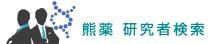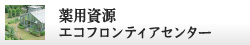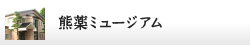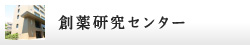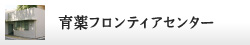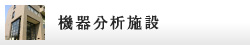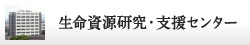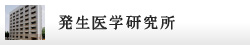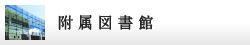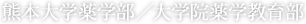薬学教育部長のあいさつ
『自らを磨く場としての熊本大学大学院薬学教育部』
薬学教育部長 香月 博志

熊本大学における薬学分野の大学院教育は、昭和24年(1949年)の熊本大学の発足ならびに薬学部の設置から15年後の昭和39年(1964年)に、大学院薬学研究科修士課程が設置されたことに始まります。その後昭和60年(1985年)の大学院薬学研究科博士課程の設置を経て、平成15年(2003年)には医学系・薬学系教育研究組織の統合・改組に伴い、大学院生の所属組織としての大学院薬学教育部が設置されました。さらに、平成18年(2006年)の学士教育課程改組に伴う6年制学科(薬学科)ならびに4年制学科(創薬・生命薬科学科)の設置を受け、各学科の卒業生を対象とする大学院の課程・専攻が平成22年(2010年)以降順次設置され、現在に至っています。

現在の熊本大学大学院薬学教育部は、6年制学士課程の卒業生を主な対象とする医療薬学専攻(4年制博士課程)と、4年制学士課程の卒業生を主な対象とする創薬・生命薬科学専攻(2年制博士前期課程および3年制博士後期課程)の2専攻で構成されています。
医療薬学専攻の大学院生は、入学時に医療薬科学コースと臨床薬学コースのいずれかを選択することになります。医療薬科学コースは主に6年制学士課程卒業後直ちに大学院に進学する学生を対象としており、専門分野における国際的研究能力を有する研究者・教育者となる人材の育成を目的としています。臨床薬学コースは主に医療現場等に在職している社会人大学院生を対象としており、高い研究志向と問題解決能力を有する高度医療専門職業人の育成を目的としています。
創薬・生命薬科学専攻についてもコース制が敷かれており、大学院生はドラッグデリバリーコース、メディシナルケミストリーコース、バイオファーマコース、ライフサイエンスコースのいずれかに所属することになります。これらのコースは医療薬学、物理系・化学系薬学、生物系薬学および生命科学に細分化された専門研究領域に対応しており、それぞれの所属コースにおいて高度な専門性を身につけられるようなカリキュラムを編成しています。
さらに、博士課程(医療薬学専攻)および博士後期課程(創薬・生命薬科学専攻)の学生のうち採用選考を通過した者については、熊本大学が全学的に展開している異分野共創型博士イノベーター育成プログラム(通称Better Co-Beingプログラム)のプログラム生として、生活費相当額の支給を受けながら独自のプログラム科目を履修し、より大きなスケールで自らの研究力・課題解決力を高めていく道も用意されています。
大学院薬学教育部に所属する大学院生の研究指導を行う研究室は、薬学・生命科学を支える多様な研究領域(28研究室:令和7年度時点)で構成されています。各研究室では、未来の創薬・医療の開拓や生命科学の進歩に大きく貢献する最先端の研究が展開されており、重要な研究成果が続々と公表されています。また、専門性の異なる研究室間での共同研究も盛んに行われています。複数の薬学系教員が主体的に運営に関わっている大学院生命科学研究部附属グローバル天然物科学研究センターならびにワクチン開発研究センターでは、世界中の薬用天然資源を基にした新薬の創出を目指した研究や、画期的ワクチンの開発に向けた先端的研究が展開されています。大学院生の皆さんもこれらの研究に携わることで、薬学・生命科学の専門家としての資質・能力が磨かれていくことになります。
高齢化社会の進展や医療技術の進歩など、世の中の目まぐるしい変化に対応しながら社会に貢献を続けていく人材には、生涯にわたって研鑽を続け、専門家としての資質・能力を高めていくという姿勢が求められます。逆に言えば、そういった姿勢を保ち続けられる人材は、どのような環境においても生き抜いていける地力があるということです。大学院に進学し、博士課程・博士後期課程を修了して博士の学位を取得することは、自身に「地力」があることを客観的に示す証明書を手に入れることと同義と言えます。大学院生の皆さんには自らを磨く場として、熊本大学大学院薬学教育部の魅力的な教育研究環境を存分に活用してほしいと思います。