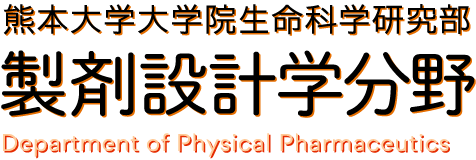当研究室は、1973 年 4 月に熊本大学薬学部(熊薬)13 番目の講座、「製剤学教室」として開設されました。開設当初の講座主任は学部長の一番ヶ瀬尚教授が併任され、1974 年 7 月名古屋市立大学薬学部より上釜兼人先生(当時助教授・現熊本大学薬学部名誉教授)が研究室を主催されました。1985 年 4 月大学院薬学研究科(博士課程)の設立を契機に大講座制が発足し、「製剤学教室」は医療薬剤学講座を構成する「製剤学研究室」に改称されました。また、この時期に、関東、関西、九州近隣地区で製剤学研究室の同門会が設立されました。2003 年大学院の部局化により、研究室名も「製剤設計学分野」に変更されましたが、同門会は発足当時の研究室名を残して『製剤学研究室同門会』として現在も活動しております。同門会員は、教職員・旧研究生・卒業生・修了生で総勢 330 名に上り(2019 年 4 月時点)、様々な企業や医療機関にてご活躍されております。5 年毎に同窓会の周年事業を行い、2019 年は製剤学研究室創立45周年を迎えます。また、各同門会支部では定期的に同門会を開催し、世代を超えて交流を行い、親睦を深めております。
当研究室は、多くの同門の皆さまのご理解とご支援を頂いております。室員および研究室に所属する研究生および学生は、同門の皆さまに常に感謝の気持ちを忘れることなく、研究教育に励んでおります。
関東支部会長 矢野 秀樹(平成 7 年度卒)
関西支部会長 宮本 祐司(平成 10 年度卒)
九州近隣支部会長 山口 美信(平成 8 年度卒)
【製剤学研究室創立 50 周年開催報告】
熊薬製剤学研究室 50 周年事業を開催致しました。非常に多くの皆さまにご出席いただきましたこと、厚く御礼申し上げます。また、ご出席が叶わなかった方からもたくさんの記念品代をお預かりいたしました。心より御礼申し上げます。55周年、60周年、100周年と研究室が益々発展していけるよう、鋭意努力して参りたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
令和6年 11 月吉日
製剤設計学研究室
本山、東
製剤学研究室創設50周年記念祝賀会 上釜兼人先生 御挨拶 (以下原文を掲載)
皆様こんばんは 上釜兼人です。ご指名によりましてご挨拶を申し上げます。
まず初めに、本日はお忙しい中を多数の皆様がご参集くださいまして、誠にありがとうございます。そして、このように盛大な記念行事を企画・実施してくださいました製剤学研究(製剤研)の教職員、学生の皆様、並びに関東、関西、九州近隣地区同門会幹事の皆様に心から御礼申し上げます。
さて、製剤研は、大学院博士課設置による熊大薬学部(熊薬)のさらなる発展を願って、1973年4月に新設されました。当時33歳の私は、名古屋市立大学薬学部から学部長直属の助教授として1974年3月熊薬に赴任し、1979年に教授昇進を契機に、 5年毎に創立記念行事が開催されるようになりましたので、今年で50周年を迎えました。50周年でめでたい記念日と言いますと金婚式が有名ですが、次の55周年はエメラルド婚、60周年はダイヤモンド婚と称する記念日があります。世界で一番硬いとされるダイヤモンドのように「固い絆を持つ夫婦である」ことからダイヤモンド婚と名付けたそうです。
我々製剤研も新旧教職員・学生・同門会が硬い絆で結ばれ、輝かしい歴史と伝統を築き、創立50周年を迎えたことは、大変嬉しく、誇らしく思います。そして、次の55周年に向けて本山教授と東准教授が率いる新生製剤研のさらなる発展を祈念いたします。
ところで、念願の博士課程設置は石油ショックなどの経済不況で政府予算が滞り、1985年4月に実現しました。製剤研からは菊池正彦君が第一号の博士課程修了者となり、彼に続いて現在まで50名の課程博士と20名の論文博士が誕生し、国内外の製薬企業・大学・医療機関などで活躍されていることは大変喜ばしい限りです。
さて、本日は若い世代の方々が多数出席されていますので、薬学部そして製剤研にとりましても重要な出来事を少しお話いたします。私は熊大勤務32年間の中で、管理運営や社会貢献面の用務が多かったことから、研究活動に停滞がないように、平山先生、小田切先生、入江先生、今井先生、有馬先生、そして歴代の大学院生諸氏に多大なる協力をお願いして、切り抜けてまいりました。とくに、学部長任期中の4年間は、重要課題が山積し、独立行政法人化に伴う大学院の組織改革などの対応で文部科学省の医学教育課に何度も足を運びました。 とりわけ、薬学教育の年限延長問題をどう決着するか、全国の薬学部教授会で一斉に議論が行われました。タイムリミットの1999年は、奇しくも熊薬が国公立大学薬学部長会議の幹事校であったことから、私がとりまとめ役となって協議を重ね、4+2体制、すなわち、「創薬研究者養成の4年制課程と薬剤師養成6年制課程の併設:その比率は各大学に任せる」を成案として、私立薬大側と最終的な合意を得ました。その結果、入学定員当たりの6年制採用枠は、大半の私立薬大が100%、一方、国公立大学は、東大15%、京都大20%、九大40%、などと創薬研究者養成に重点が置かれ、長崎大50%、熊薬は60%と苦渋の選択でした。この決議に基づいて、平成18(2006)年4月から、薬学部に2つの教育課程が発足し、教務委員長の入江先生には、新カリキュラムや実務実習の立ち上げに大変ご苦労をおかけしました。私は、ストレスの多い用務に対する気分転換を兼ねて、教室旅行や学部長杯のソフトボール大会、各種コンパに積極的に参加しました。また、学生諸君と国内外のシンポジウムに参加して、著名な研究者や友人達と交流を深めながら、シクロデキストリンの医薬への応用研究を推進しました。
教育面に関しまして、私は国内外の 7つの大学の薬学部、すなわち、東京薬科大学(卒)→東北大学→米国カンサス大学→名古屋市立大学→熊本大学→崇城大学→サウジアラビアの王立大学に在籍して得た様々な知識や経験を「製剤学」の講義・実習のスキルアップとテキスト作成に活用しました。また、新設の崇城大学薬学部に勤務中には、瀬尾先生や石黒先生の協力を得て薬剤師養成教育における基本的事項を学び、学生の就職活動の支援を行いました。
2014年秋、40年に及ぶ熊本の生活に終止符を打って、息子たちが住む横浜に移住し、旧友たちとの再会を楽しみました。ところが、人生の最終章をむかえて、新型コロナ感染は何とか免れましたが、予期せぬ「癌」の洗礼を受けました。プライベートな話で恐縮ですが、私は昨年5月、前立腺癌を告知され、放射線治療を選択しました。一方、家内は今年の3月に突然の高血糖で膵臓癌が発覚して手術を決行し、現在、夫婦共々経過観察中です。近年の医療・医薬・検査法の進歩、介護サービス事業の充実などのお陰で安心して治療に専念できるのは大変有難く、周囲の皆様のご支援とご厚情に感謝しつつ、プラス志向で「癌」と対峙しています。そして、最初にお話しましたダイヤモンド婚を視野に入れながら、癌の増殖・転移を抑制可能なシクロデキストリンを用いた安全で使用性に優れるDDS製剤の開発を夢見ています。
最後に、終の棲家となりました横浜から、熊薬製剤研並びに同門の皆様の益々のご健勝を祈念して、ご挨拶といたします。御清聴ありがとうございました。
【製剤学研究室創立 45 周年開催報告】
熊薬製剤学研究室 45 周年事業へ多くの皆さまにご出席いただき、事務局として心より感謝申し上げます。また、ご事情により出席いただけなかった方も記念品代を拠出いただくなどご協力いただき心より感謝申し上げます。今回、上釜先生ご夫妻を熊本にお迎えし、ご受勲(瑞宝中綬章 勲3等)を皆さまでお祝いできたことは、本当に喜ばしいことでした。改めまして、45周年事業をお世話頂きました、各同門会支部長と役員の皆さま、そして同門の皆さまに深く感謝申し上げます。一方で、研究室に対しても激励のお言葉を数多く頂きました。教員一同、鋭意努力して参りたいと思いますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
令和元年 11 月吉日
製剤設計学研究室
本山、東、小野寺
製剤学研究室創設45周年記念祝賀会 上釜兼人先生 御挨拶 (以下原文を掲載)
皆さまこんばんは!
本日はご多用中のところ、製剤学研究室創設 45 周年記念祝賀会にご参集くださいまして誠に有り難うございます。本来なら、現役の主任教授がご挨拶すべきところでありますが、昨年、予期せぬ事態が発生し、今年 3 月に退職しましたので、前職の私が務めさせていただきます。それではこれから皆様へのお願いを込めて、いくつかお話し致します。
まず始めに、現在の製剤学研究室は、残された若手教員を菊池君を中心とした先輩諸氏が強力にサポートしながら、学生さんの教育研究指導や様々な対外活動に頑張っておられます。そこで皆様へのお願いですが、このような現状は研究室存亡の危機と言っても過言ではありませんので、伝統の「製剤魂」、即ち強固な団結力と相互補助の精神で、研究室の存続・発展に今後とも、ご支援を賜りますようお願い致します。私も及ばずながら、熊本を訪れるたびに、製剤の学生さん達に、最新のバイオ医薬品や機能性化粧品に関する基礎的な講義を実施しています。
ところで、国立大学法人の教員には、教育、研究、管理・運営、地域や国際社会への貢献など様々な業務が課されますが、これらをすべてカバーするのは容易でありません。幸い私には、小田切、平山、入江、今井、有馬先生と素晴らしい協力者がいました。そして、学外から多数の同門生の皆様が親身になって支援してくださいました。今後は、本山、東、小野寺先生が協力して、新しい製剤学研究室を築いていただきたいと期待しています。
話は急に変わりますが、「As time goes by」、訳して「時は過ぎゆくまま」という古いアメリカ映画の主題歌があります。 第二次世界大戦中、フランス領モロッコの「カサブランカ」を舞台にしたラブロマンスですが、 この映画の時代背景である 1941 年は、奇しくも私が生まれた年ですので、親近感から、何度もビデオを見直しました。「As time goes by」の歌詞には、「どんなに時代や生活環境が変ろうとも、自分が正しいと信じる道を変えることなく、前進しましょう」という意味が込められています。この曲は、現在の製剤研の皆様にも直面する課題や今後の研究教育の展開を考える上で、勇気と安らぎを与えてくれるものと思います。
次の話は、私ごとで恐縮ですが、この夏、熱中症と肺炎を患らい、救急車で搬送されました。3 週間入院しましたので、家内も看病疲れで体調をくずし、あわや共倒れになりそうでした。病院のベッドでは、製剤の教室旅行やバーベキュー大会など楽しかった行事を懐かしく思い出しました。縁あって皆様と熊本で出会い、共に喜び、励まし合い、熱く語り合った日々は、大切な思い出として、今後も深く心に留めていく所存であります。もう一つ、これはご報告ですが、令和元年秋の叙勲に際しまして、はからずも瑞宝中綬章の栄誉に浴することになりました。勲記・勲章の伝達と天皇陛下への拝謁は 12 月 13 日に挙行されます。これも偏に皆様の長年にわたるご支援、ご厚情の賜であり、深く感謝いたしております。最後になりましたが、今回の記念行事の開催に尽力されました関東・関西・九州近隣地区同門会支部長、ならびに、事務局として運営の労をとられました製剤学研究室の教員と学生さんに厚く御礼申し上げます。そして、このような盛大な記念行事が 50 回、60 回と継続するよう祈念しまして、ご挨拶に代えさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。