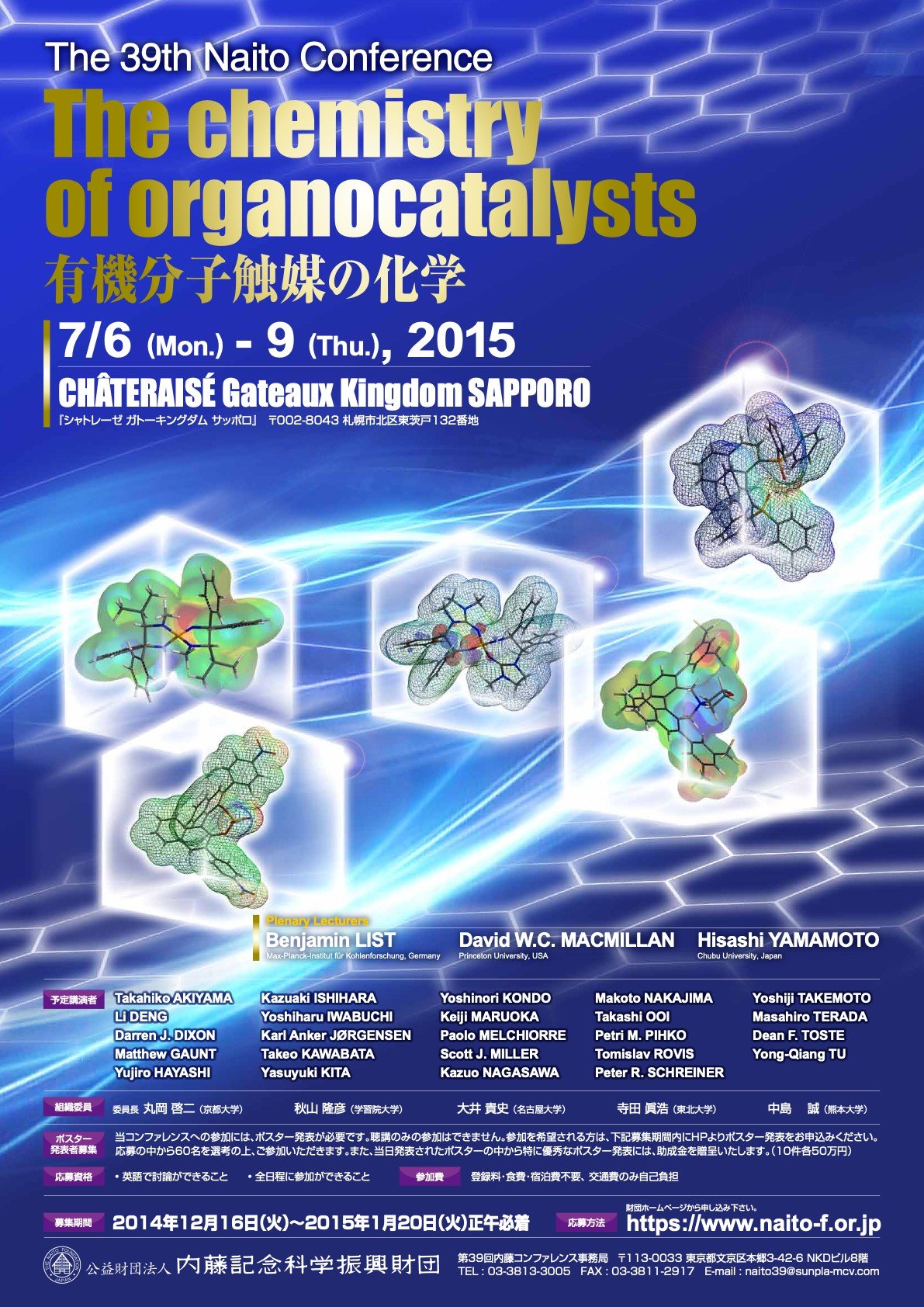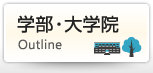2021年のノーベル化学賞は、「不斉有機触媒の開発」に成功したMax Planc研究所のBenjamin List氏とPrinceton大学のDavid MacMillan氏に授与されました。これまで、高価であった金属化合物からなる触媒を、両氏は、金属を用いない純粋な有機化合物から調製しました。この触媒を用いることにより、医薬品の主成分となる生物活性物質などを、環境への負荷を減らしつつ効率的に合成することができるようになりました。この研究分野には、多くの化学系薬学研究者が携わっています。
詳しくは以下の通りです。
↓ ↓ ↓
2021年度ノーベル化学賞について
分子薬化学分野・中島 誠
2021年度のノーベル化学賞は、Max Planc研究所のBenjamin List氏とPrinceton大学のDavid Mac Millan氏が受賞された。両先生にお祝いを申し上げるとともに、受賞理由となった「不斉有機触媒」について、同じ領域の研究者としてその内容を解説したい。
「不斉」とは非対称という意味である。医薬品を含む生物活性物質の多くは非対称であり、その鏡像異性体(右手用手袋と左手用手袋の関係にある異性体)が存在する。医薬品として利用する際は、それらを厳密に区別する必要があるが、それらを人工的に合成する際、通常の方法ではそれら両者の等量混合物ができてしまう。所望の一方のみを合成するために必要なのが「不斉触媒」であり、その開発により野依良治氏(当時 名古屋大学)は2001年度ノーベル化学賞を受賞している。
ところで、世の中に数多く存在する触媒、例えば、洗面台の鏡の曇り止めに塗ってあるチタン触媒、車の排気口に装着されているパラジウム触媒など、ほとんどの触媒は、金属化合物である。生体内の触媒である酵素に関しても、活性部位にはほとんど金属イオンが存在している。有機合成の分野でも、触媒の多くは金属化合物である(2001年ノーベル化学賞を受賞した野依良治氏はロジウム触媒やルテニウム触媒、2010年ノーベル化学賞を受賞した鈴木章氏はパラジウム触媒を利用)。しかし触媒に利用される金属の多くは、地球上には稀にしか存在せず、採掘に大きなエネルギーを要すため、高価なものが多い。また、場合によっては政治的理由から入手が困難になることもある(中国から輸入していたレア・アースの件を想起してもらいたい)。さらに、昨今では、反応後、環境問題からむやみに廃棄することが難しいため、工業的に利用するときには万全の注意が必要となる。もし金属を全く含まない、C, H, N, O, Pなどのみから触媒を作ることができれば、そうした問題群を一気に解決することができるはずだ。List氏とMacMillan氏は、金属を用いない純粋な有機化合物からなる不斉触媒を開発したことが、今回の受賞に至った。
と、ここまではインターネットや全世界の新聞で紹介されているものと同じ内容であろう。同じく「不斉有機触媒」の開発研究を行っていた筆者がもう少し説明を加えたい。両氏の受賞の端緒となる論文が発表された2000年前後の有機合成化学の領域では、ダイレクト・アルドール反応(簡便で高選択的なアルドール反応の一種であり、それだけでノーベル化学賞受賞テーマになり得る)の開発が大きな潮流にあった。2000年から2002年にかけて、List氏とMacMillan氏は、それぞれ独自に、アミノ酸の1種であるプロリンを触媒とするダイレクト・アルドール反応に関する複数の論文を次々に報告した。実はプロリンを触媒とするアルドール反応は、すでに1970年代にHajos氏らにより報告されていたが、ステロイドのCD環を構築するという、きわめて限定的な反応であったため、それほど多くの注目は浴びていなかった。List氏とMacMillan氏は、それを一般的な基質に拡張したものであった。しかしここで注目すべきは、MacMillan氏が「有機触媒Organocatalyst」という用語を発明したことだ。両氏は、それ以降、アルドール反応に限らず、多くの有機触媒反応を開発していくことになる。
実は、Hajos氏らに限らず、金属を用いない有機分子を触媒とする反応は、マイナーではあるものの世界各地で研究が続けられていた。プロリンから離れ、「有機触媒」という概念が世に出たとき、「あれ?うちの触媒って有機触媒じゃね?」と声を出した研究者は筆者だけではなかったはずだ。筆者は、それまで触媒としては認識されていなかったN-オキシドやホスフィンオキシドが不斉有機触媒としてアルドール反応などを促進することを報告したばかりだった。筆者以外にも、特に日本国内には有機触媒に携わる研究者は少なくなかった。2004年、日本化学会の会員誌「化学と工業」に有機触媒特集号が組まれ、2011年には科研費「新学術領域」において東北大学の寺田眞浩氏を代表とする「有機分子触媒による未来型分子変換」がスタートした。2015年、札幌で開催されたシンポジウム「有機分子触媒の化学」(組織委員長:丸岡啓二氏)では、List氏とMacMillan氏が基調講演者であったが、それ以外に14名の日本人研究者が講演を行なった。多くの優れた日本人研究者がこの領域を牽引してきたが、その中から貢献度が大きい一人を敢えてあげるとすれば、それは京都大学の丸岡啓二氏であろう。丸岡氏が開発した「丸岡触媒」は、開発後まだ日が浅いにもかかわらず、人工アミノ酸の工業的合成に利用され、すでにいくつかの治験薬の合成過程で活躍している。これらの成果から、氏は、日本学士院賞をはじめ、海外を含めた多くの学会などから賞を授与されている。勿論、List氏とMacMillan氏の功績は受賞に相応しいものではあることは間違いないが、3人枠であるノーベル賞の3人目に丸岡氏が加えられなかったのは極めて遺憾である。さらに言えば、両氏が最初に報告したのは「プロリン触媒」を用いた「ダイレクト・アルドール反応」なのだから、もし今回の受賞テーマが、「化合物」ではなく「反応」だったら、すなわち「有機触媒」ではなく「ダイレクト・アルドール反応」だったら、その最初の発見者である柴崎正勝氏(現 微化研、元 東大薬教授・日本薬学会会頭)が両氏と同時に受賞していたであろう。いずれにせよ、今回のノーベル化学賞受賞には、日本人研究者は紙一重で手が届かなかったのである。
とにもかくにも、「有機触媒」が檜舞台にあがったのは大変喜ばしいことで、今後のこの領域の発展に大きく貢献するであろう。個人的にも、分野外の人に自分の研究を説明するのがやや簡単になったことはありがたいことである。有機触媒反応は、昨今のSDGsにかなった有機合成反応であり、今後も進展していくのは間違いないが、これをきっかけに、多くの若い人が科学に興味を持ってもらうようになることを期待する。
(図は、2015年に行われた札幌で行われたシンポジウムのポスター)