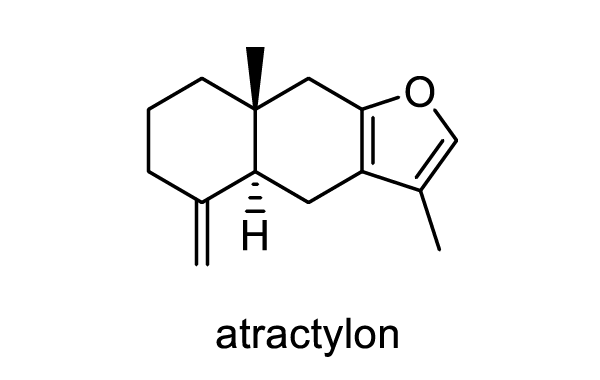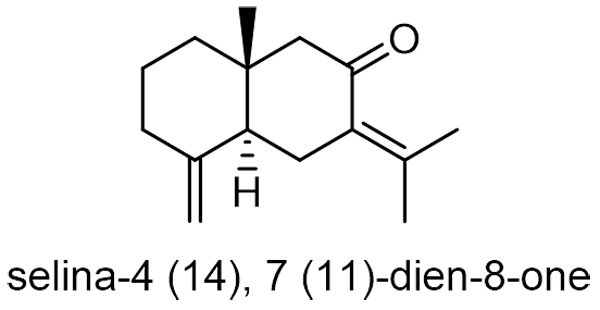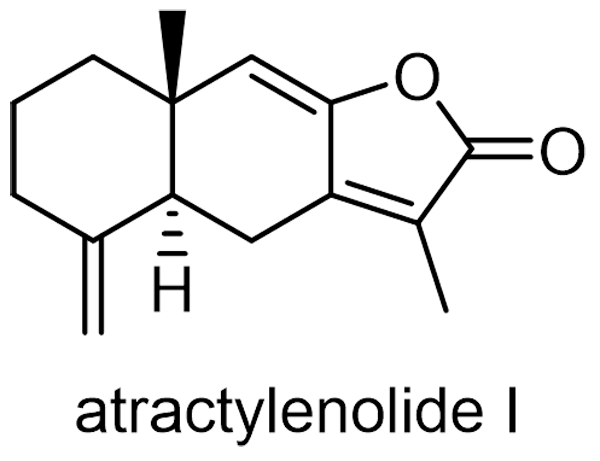キク科
Asteraceae
オケラ
Atractylodes ovata (Thunb.) DC.
00:00 / 00:00

- 英名
- Japanese atractylodes
- 中国名
- 関蒼朮
- 花期
- 9~10月
- 生薬名
- 白朮(ビャクジュツ)【局】
- 薬用部位
根茎
- 産地と分布
-
本州,四国,九州,および朝鮮,中国東北部に分布し,日当たりのよい山地の乾いた所に多い.
- 植物解説
-
多年草.根茎は長く,草丈30~60 cm.硬くて円柱形.葉は互生,長柄があり,羽裂または楕円形.枝の頂に白色または紅色の頭花を付ける.雌雄異株.オケラの語源は古名ウケラがなまったものとされるが,ウケラの語源は不明.
- 薬効と用途
-
健胃,利水(体の水分代謝を調える)作用があり,食欲不振,腹部膨満,下痢などの症状に用いる.漢方処方では帰脾湯,半夏白朮天麻湯などに配合される.同属のホソバオケラの根茎は蒼朮と呼ばれ,白朮と使い分けがなされるが,用法に混乱が見られる.一般的に,白朮は蒼朮よりも健胃作用が強く,利水作用は弱いとされる.
「山でうまいはオケラにトトキ(ツリガネニンジン)」と謳われ,若芽は山菜としてごま和えなどで食べられる.熊本県では生育環境の悪化により絶滅寸前である.
参考文献についてお知りになりたい方はお問い合わせください。