 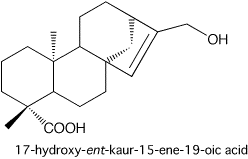 |
『バナナ月 山路のきわに 宇登呂花』(河童)
ウド植物の名前の由来を調べてみると”茎が生育すると中空となるので宇登呂(ウドロ)と呼ばれそれが省略されウドとなったといわれている”とある.確かに山菜で食べる春先の若い芽は芯のつまった茎で、春の香とほろ苦い味がする.天ぷら、あえ物にして食すと旨い.しかし、花が咲く時期になると茎はストロー状に中空になる.冬の枯れた茎で笛を作ることも出きる.
薬用部位としては根を用い、生薬名”独活”(ドッカツ)と言います.独活の基源植物には、ウドAraria cordata Thunberg)の他に、セリ科 (Umbelliferae) のシシウド (Angelica pubesens Maximowicz)またはその近縁種の根が唐独活としてもちいられています.性味は.辛苦、温.効能は、感冒を直す、湿を除き、体を温め、寒を散らします.止痛などで、風寒湿痺、腰膝の痛み、手足の痙攣痛等に、十味敗毒湯、独活湯、荊芥敗毒湯等に配合されます.
ウドの仲間には、同じウコギ科のヤツデ、カクレミノ[葉、花]、薬用人参、チクセツニンジン、エゾウコギ等がある.どれも花、果実が梵天(玉)状につくのが特徴です.
独活で思い出すのは、30年前広島大學大学院総合薬学研究科生薬学研究室修士に入学し最初のテーマが独活から新規な化合物の分離でした.薄暗い戦前の赤煉瓦の建物が研究室です.一回生のマミ子さんが単離し残していったマミコ酸と名付けられた1:2の混合物100mg位の結晶を分け、構造を解析するテーマをいただきました.だいたいの構造式は分かっていましたので、手を黒くしながら硝酸銀シリカゲルを準備、一回のカラムクロマトで、30mg位ずつ単離しました.その後これを合成しなさいといわれ、光増感酸化反応を行いましたが、最初は、300Wの電球をあててもうまくいきません、その内夏休みになり、家の果樹園の手伝いも有り、1ヶ月助手の先生にお願いし、太陽の当たるところに日中だけおいてもらいました.帰ってきて反応液を確認すると目的の化合物が有るではありませんか.これ幸いと分離しました.後は収量を上げただけで、報告が出来ました.mamikoic acidで報告を出したかったのですが、植物、生薬との関連もなく、その構造は17-hydorxy-ent-kaur-15-ene-19-oic acidです.私のウコギ科植物研究との付合いの始まりです.次が薬用人参Panax属の研究で、今も薩摩竹節人参のルーツをヒマラヤ、中国に探しています.夢を見ながら.
”独活”は(株)ツムラ、”カクレミノ”は森林総合研究所九州支所のリンク許可をいただきました.
写真2003年9月13日(星薬科大学薬用植物園)撮影
(資料,写真・文章責任 薬学教育部・付属薬用植物園(Medicinal Botany and Ethnobotany )(Molecular Evaluations of Medicinal Plants)、・矢原 正治,2003.10.2)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
トップページへ戻る |

