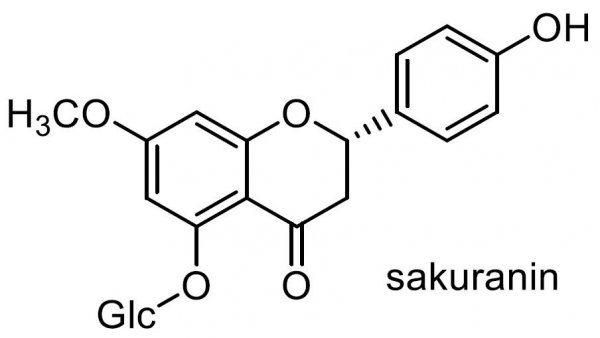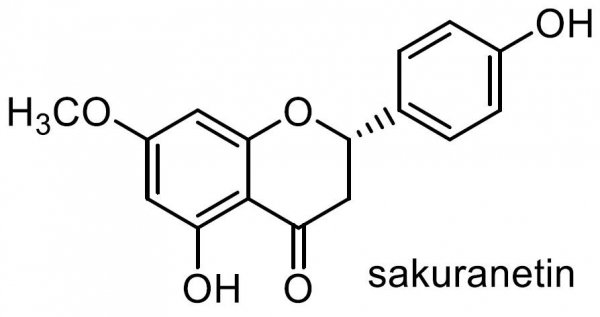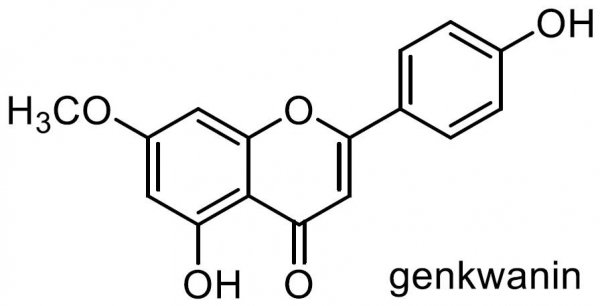バラ科
Rosaceae
オオシマザクラ
Cerasus speciosa (Koidz.) H.Ohba

- 英名
- 中国名
- 大島桜
- 花期
- 3~4月
- 生薬名
- 桜皮(オウヒ)
- 薬用部位
樹皮
- 産地と分布
-
伊豆諸島に分布し,房総半島,三浦半島,伊豆半島(自生との説もある)をはじめ全国の沿海地の丘陵地や低山に薪炭材として植えられたものが野生状態で生えている.
- 植物解説
-
落葉高木.樹高15 m.樹皮は紫黒色または灰紫色で,濃褐色の縦長の皮目が目立つ.若葉は緑色で赤みを帯びない.葉柄は無毛,葉身は倒卵形または倒卵状楕円形で,縁には一部が2重となった著しい芒状の鋸歯があり,両面無毛.蜜腺は葉柄の上部に付く.花は葉と同時期に開き,花序は3~4花からなる散房花序となる.
- 薬効と用途
-
解毒,解熱,鎮咳作用があり,魚の中毒,じんましん,腫れ物などの皮膚病,咳,発熱などに用いる.日本では江戸時代,民間薬として多く使用された.本種は日本薬局方での生薬桜皮の基原ではない.
成長が早く,萌芽力が旺盛であるため薪炭材として利用された.葉を塩漬けすると芳香を有するクマリンが発生し,桜餅の原料となる.本種以外の桜でもよいが,葉が大きい上に芳香が強いため重用される.伊豆地方の松崎町が主産地で,採葉用の桜畑が造成され,全国の総生産量の70%を占めている.
ソメイヨシノは本種とエドヒガンとの間に生じた雑種の名称である.このためエドヒガンに近似するものからオオシマザクラに近似するものまで変異が大きい.その中で,‘染井吉野’は観賞用に全国で広まっている栽培品種.
参考文献についてお知りになりたい方はお問い合わせください。