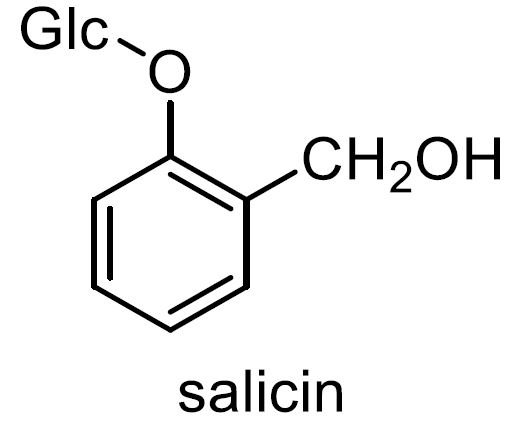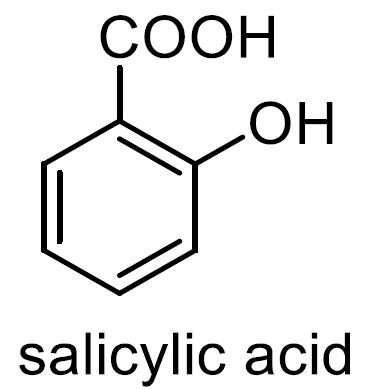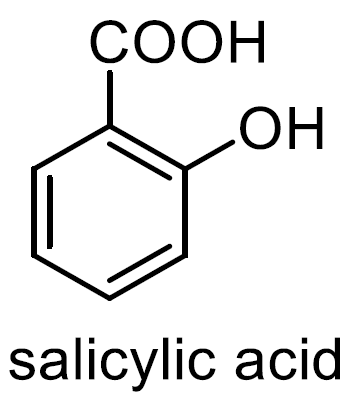ヤナギ科
Salicaceae
イヌコリヤナギ
Salix integra Thunb.
00:00 / 00:00

- 英名
- 中国名
- 杞柳
- 花期
- 3月
- 生薬名
- 薬用部位
樹皮
- 産地と分布
-
北海道から九州,および南千島,朝鮮北部,中国東北部,ロシア(ウスリー,アムール,沿海州)に分布し,水辺や湿潤の地に生える.
- 植物解説
-
落葉低木.樹高2~3 m,稀に6 mに達する.冬芽は卵形で紅紫色.葉は対生あるいは互生し,多くは無柄,ときに有柄で長さ約5 mm.成葉の葉身は狭長楕円形または長楕円形,ときに狭卵状長楕円形,長さ4~8(-10)cm,幅1.5~2 cm,鋭頭ないし鈍円頭で微凸端,基部は円形ないし浅心形,両面とも無毛,低い再鋸歯がある.托葉はない.花穂は葉より先に現れ,細長い円柱形で密に花を付け,斜上ないしほとんど水平に開出し,柄は短く,小型の葉3~4個を付ける.
- 薬効と用途
-
ヤナギの仲間は世界に多くの種類があるが,どの種にもsalicinやsalicylic acidが含まれている.そのため世界中で解熱薬,鎮痛薬として利用されている.Salicylic acidをヒントに合成されたacetylsalicylic acidはアスピリンの名で知られ,今日でも解熱鎮痛剤として広く利用されている.日本ではヤナギで作った楊枝(ようじ)を使うと歯が痛くならないとされる.
参考文献についてお知りになりたい方はお問い合わせください。