
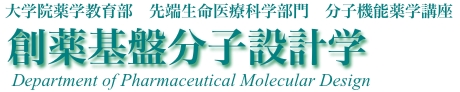

当研究室の運営方針
学部配属生にしても大学院生にしても、研究室においては教育の中心となるのは研究である。最近、問題解決力をつける教育、ということが強調されることが多く、さまざまな課題を解決する練習を行うようなことが推奨されているが、とんでもない話である。
問題解決力云々、は、今までの知識偏重教育や、一分野に偏った専門教育に対する非難から来ているものであろうが、「問題が与えられたら解決できる」だけでは役には立たない。それでは、指示待ち症候群、と呼ばれるものと大して変わらない。
大切なのは、「問題を発見する力」 である。さまざまな事象の中から、解決すべき問題を取り上げ、解決するための手段を考案し実行する。この能力こそが、私が考える、真に必要な能力である。(もちろん、それを解決する、ことが大事であることは言うまでもない)
研究を行う際には、目標に到達するために「何をすべきか」を考えることがまず必要である。解決すべき問題、を自分で設定する必要があるわけである。
しかし、最初から、そういうことが出来る人はほとんどいないから、心配しなくてもよい。当研究室においては、一緒に考えながら目標に向かっていくことで、少しずつでも、そういうことが出来るようになるように研究を進行する。
もちろん、ただ実験すればよいというものではない。勉強しなくてはいけないことはたくさんある。
学習指導要領の改悪のおかげで、小学校から中学校、中学校から高校へと、本来知っていなければいけないことの教育が先送りされ、高校の科目選択のため(あるいは受験指導のため)に本当に重要なことを知らないまま大学に入ってくる学生が最近多い。そのために、大学の学部教育のスタートレベルが下がり、通常の授業では、なかなか以前と同じレベルの内容まで到達することが出来なくなってきている。
それらに関しては、大学院などで教育することが必要であるのは言うまでもない。研究室においては、研究に必要なものを中心に、それらの教育を行っていく。 当研究室の研究分野は有機合成化学であるが、有機化学に固執することなく、化学に関することはバランスよく学習出来るように考慮していく。
化学だけ? と思うかもしれない。
専門バカ、と言う人もいるかもしれない。
専門バカ 結構じゃないかと思う。「専門もバカ」よりずっとマシである。
世の中、専門のことしか知らないではやっていけないのは言うまでもない。広くいろんなこと知る必要は、ある。だが、専門のことにまず詳しくなってから、他のことに手を付けてもよいのではないか?
最終的に「専門バカ」というのは困る。でも、一時的になら・・・・専門バカと言われるくらい一つのことに集中してみてもよいのではないだろうか?
大学院がそういう期間であってもよいのではないかと私は思う。 (あくまで私見である。違う意見の人もたくさんいるはずだ。)
英語に関しても、専門文献ばかりでなくTOEICなどを素材として、将来どのような職業に就くにしても役立つようにするつもりである。
尚、当研究室においては、個人個人に独立したテーマが与えられ、それに関して実験研究が行われる。先輩のテーマに関連したテーマ、を与えられることはあるだろうが、先輩の実験のお手伝い、をさせられることは、ない。学会前などで、研究室総力でデータ作成をすることはあるだろうが、通常はおのおのが独立した研究者として扱われる。責任は重いが、やりがいもあるシステムであるはずである。
興味ある方は、一度見学に来ることを勧める。大学院進学などの相談も、いつでも受けるので遠慮なく研究室に遊びに来て欲しい。