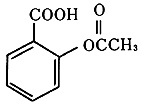
化学名
2-acetoxybenzoic acid
分子式
C9H8O4
分子量
180.16
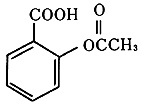
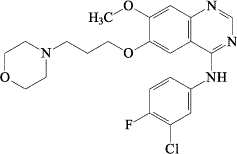
| アスピリン | 効能 | 重要な基本的注意 | 重大な副作用 |
| イレッサ | 効能 | 重要な基本的注意 (警告) | 重大な副作用 |
|
医薬品の情報に関しては から取っています。 医薬品機構のほうは、実際の添付文書のPDF版もありますし、構造式の表示もあります。ただ、すべての医薬品が掲載されているわけではないので御注意ください。 熊大版のほうは、テキスト情報だけですが、薬価収載されている医薬品すべて(実際には、3ヶ月遅れくらいですが)が掲載されています。 |